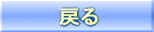| �� |
����@���̋K���́A���R�����w�Z���Ɨ��������(���a��\�l�N���R�������\�O��)�掵���̋K��ɂ��A���R�����w�Z�̎��Ɨ��̌��ƂɊւ��K�v�Ȏ������߂���̂Ƃ���B |
| �� |
����@�m���́A���R�����w�Z�̐��k(���w�������ꂽ�҂��܂ށB)���A���̊e���̂����ꂩ�ɊY������Ƃ��́A���̎��R�̐���������ɔ[���̓������錎���̎��Ɨ��̑S����Ə����邱�Ƃ��ł���B�������A���Y���R�̐��������O�ɔ[�����ꂽ���Ɨ��ɂ��ẮA�Ə����Ȃ��B |
| �� |
�����ی�@(���a��\�ܔN�@����S�l�\�l��)�Ɋ�Â��ی���Ă��鐢��(�ی�̒�~���̐��т��܂ށB)�̐��k�ł���Ƃ��B |
| �� |
��ʈ⎙��(���������@(���a��\��N�@����S�Z�\�l��)��Z���ɋK�肷��ی�Җ��͓��@���\�����ꍀ��O���ɋK�肷�闢�e�������Ԃ�莀�͕ʕ\���̌���Q��ꋉ�����O���܂łɊY�����邱�ƂƂȂ��҂������B)�ł��āA���̐����̍������x�����̂����ꂩ�ɊY�����鐶�k�ł���Ƃ��B |
| �C |
���Y���k��}�{����҂����Ȃ��ꍇ�ł��āA���Y���k�������Ŗ@(���a�l�\�N�@����O�\�O��)�̋K��ɂ�菊���ł�[�t���Ȃ����ƂƂȂ�Ƃ��B |
| �� |
���Y���k��}�{����҂�����ꍇ�ł��āA���Y�}�{�҂������Ŗ@�̋K��ɂ�菊���ł�[�t���Ȃ����ƂƂȂ�Ƃ��B |
| �n |
�C�y�у��Ɍf����҂Ɠ����x�ɐ������������Ă���ƔF�߂���Ƃ��B |
| �O |
�]�����ꐢ�тɂ���A��Ƃ��Đ��v���ێ����A�A�w���̎q�y�ђ햅�̊w���S���Ă����(���R�����w�Z�莞���ے����k�̂����ΘJ���Ă��鐶�k�ɂ��ẮA���Y���k)���n���Ŗ@(���a��\�ܔN�@�����S��\�Z��)�̋K��ɂ��s�������ł�[�t���Ă��Ȃ��Ƃ��A���͎s�������ł̋ϓ����݂̂�[�t���Ă���Ƃ��B |
| �l |
�O�O���̏ꍇ�������A�]�����ꐢ�тɂ���A��Ƃ��Đ��v���ێ����A�A�w���̎q�y�ђ햅�̊w���S���Ă���҂����S���A���͐��_�Ⴕ���͐g�̂̏�Q�A�ЊQ���̑��̎��R�ɂ�萶���ɍ������A���Ɋw���S����҂��Ȃ��ƔF�߂��鐶�k�ł���Ƃ��B |
| �� |
�O���@�O���̋K��ɂ����Ɨ��̌��Ƃ��悤�Ƃ���҂́A���Ɍf���鎖�����L�ڂ����\�����𑬂₩�ɒm���ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �� |
�ی�ҋy�ѐ��k�̏Z���A�����y�ѐ��N���� |
| �� |
�w�Z�� |
| �O |
���Ƃ�\�����鎖�R |
| �l |
���̑��K�v�Ȏ��� |
| �Q |
�O���̐\�����ɂ́A���Ɍf���鏑�ނ�Y���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �� |
�O���ꍆ�ɋK�肷��ꍇ�ɂ��ẮA�����ǒ����͕������������̏ؖ��� |
| �� |
�O���ɋK�肷��ꍇ�ɂ��ẮA�ی�Җ��͗��e�̎��S���͌���Q�Ɋւ���ؖ����y�є[�łɊւ��鎖��(���Y�N�x���͑O�N�x�̎s�������ł̐Ŋz�y�ѓ��Y�Ŋz�̎Z��̊�b�ƂȂ鏊���z�B�ȉ������B)�ɌW��s�������̏ؖ��� |
| �O |
�O���O���ɋK�肷��ꍇ�ɂ��ẮA�[�łɊւ��鎖���ɌW��s�������̏ؖ��� |
| �l |
�O���l���ɋK�肷��ꍇ(�ЊQ�ɂ��ꍇ�������B)�ɂ��ẮA�Œ莑�Y�]���Ɋւ���ؖ����y�є[�łɊւ��鎖���ɌW��s�������̏ؖ��� |
| �� |
�O���l���ɋK�肷��ЊQ�ɂ��ꍇ�ɂ��ẮA��Q�̒��x�Ɋւ���ؖ��� |
| �Z |
���̑��m�����K�v�ƔF�߂鏑�� |
| �R |
�O���A��O�����͑�l���̋K��ɂ����Ɨ��̌��Ƃ����҂̂����A���Y���Ƃ���N�x�̑O�N�x�̔[�łɊւ��鎖���ɌW��s�������̏ؖ�����Y���đ�ꍀ�̐\�������o�������̂́A���Y�N�x�̔[�łɊւ��鎖���ɌW��s�������̏ؖ��������߂Ē�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �� |
�l���@���Ɨ����Ƃ̊��Ԃ́A���Y�N�x���Ȃ����̂Ƃ���B |
| �� |
���@���Ɨ��̌��Ƃ��Ă���҂́A���Ƃ�K�v�Ƃ��鎖�R�̏��ł����ꍇ�́A�����ɂ��̎|���L�ڂ����͏o����m���ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �� |
�Z���@�m���́A��O���O���̋K��ɂ����߂Ē�o���ꂽ�[�łɊւ��鎖���ɌW��s�������̏ؖ����ɂ������A��O���Ⴕ���͑�l���̂�����ɂ��Y�����Ȃ����Ƃ����������Ƃ��A�O���̋K��ɂ��͏o�������Ƃ��A���͋��U�̐\���Ɋ�Â����Ƃ������̂ł��邱�Ƃ����������Ƃ��́A���Ƃ̌�������������̂Ƃ���B
|
| �� |
�����@���̋K���ɒ�߂���̂̂ق��A�K�v�Ȏ����́A�m�����ʂɒ�߂�B |
|
|
| ���@���ŊO�������ɌW�鉄�؋��������i�����j |
|
|
| �� |
����@���̏��́A�n�������@(���a��\��N�@����Z�\����)���S�O�\����̎O��̋K��ɂ��A���؋��̒����Ɋւ��K�v�Ȏ������߂���̂Ƃ���B |
| �� |
����@�n�������@���S�O�\����̎O��ꍀ�ɋK�肷��Γ�(�ȉ��u���ŊO�������v�Ƃ����B)��[������ɔ[�t����҂́A���Y�[�t���z�ɔ[�����̗�������[�t�̓��܂ł̊��Ԃ̓����ɉ����A�N�\�l�E�܃p�[�Z���g(�[�����̗�������ꌎ���o�߂�����܂ł̊��Ԃɂ��ẮA�N���E��܃p�[�Z���g)�̊������悶�Čv�Z�������z�ɑ������鉄�؋��z�����Z���Ĕ[�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �Q |
�O���ɒ�߂�N������̊����́A�[������N�̓����܂ފ��Ԃɂ��Ă��A�O�S�Z�\�ܓ�������̊����Ƃ���B |
| �R |
�m���́A�[���`���҂����ŊO��������[�����܂łɔ[�t���Ȃ������Ƃɂ��āA��ނȂ����R������ƔF�߂�ꍇ�ɂ����ẮA��ꍀ�̉��؋��z�����Ƃ��邱�Ƃ��ł���B |
| �� |
�O���@���؋��̊z���v�Z����ꍇ�ɂ����āA���̌v�Z�̊�b�ƂȂ錧�ŊO�������ɐ�~�����̒[��������Ƃ��A���͂��̑S�z�����~�����ł���Ƃ��́A���̒[�����z���͂��̑S�z���̂Ă�B |
| �Q |
���؋��̊m����z�ɕS�~�����̒[��������Ƃ��A���͂��̑S�z���S�~�����ł���Ƃ��́A���̒[�����z���͂��̑S�z���̂Ă�B |
| �� |
�l���@���̏��̎{�s�Ɋւ��K�v�Ȏ����́A�m�����ʂɒ�߂�B |
|
���� |
|
(���؋��̊������̓���) |
| �S |
�����̊ԁA�����ꍀ�ɋK�肷�鉄�؋��̔N���E��܃p�[�Z���g�̊����́A�����̋K��ɂ�����炸�A�e�N�̓�������(�e�N�̑O�N�̏\�ꌎ�O�\�����o�߂��鎞�ɂ�������{��s�@(������N�@���攪�\�㍆)��\���ꍀ��ꍆ�̋K��ɂ���߂��鏤�Ǝ�`�̊�������ɔN�l�p�[�Z���g�̊��������Z���������������B�ȉ������B)���N���E��܃p�[�Z���g�̊����ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̔N���ɂ����ẮA���Y��������(���Y���������ɁZ�E��p�[�Z���g�����̒[��������Ƃ��́A������̂Ă�B)�Ƃ���B |